カスタマー平均評価:  4.5 4.5
 医療制度改革を考える際の基礎文献 医療制度改革を考える際の基礎文献
最近、必要があって、全頁に目を通してみた。そのうえでの感想は、小泉構造改革の前に未だ曾て有らざる改革を迫られている、医療制度を考える場合の基礎文献として十分機能を果たしうる、歴史を超えた書物であるということである。 歴史叙述というものは、史観という名のとおり、どうしても著述家の生きた時代の制約を受けてしまう。しかし、この膨大な論文群がそれを免れえているとしたら、それは「病人の視点ー病人史」というかたちをとったがゆえであろう。 病人の立場は時代を超えてかわらない。そして、病む人々への同情を失った医療制度は長続きしない。そうした意味で、戦後の民主主義的医療改革と国民皆保険制度が半世紀近く継続していることの重みを、新自由主義者たちは良く考えてほしい。将来に禍根を残すような制度改革を急ぐ必要が何処にあるのか? そうしたことを問い直すとき、この書物は必読文献である。
 病人の目から見た現代医療批判 病人の目から見た現代医療批判
半世紀近くの評論活動を反映した川上武氏渾身の力作である。 二部構成で、第1部は川上武門下の研究者(それぞれの方が実践的な医療従事者であることは川上武氏の選択の視点が、たんなる研究者にはないことを示すものだろう)が各論史を書いたもの。第1章戦争と病人、第2章経済復興期の病人、第3章高度経済成長から成人病の時代へ、第4章リハビリテーション医療の登場、第5章妊娠・出産と乳児死亡・未熟児の動向、第6章戦後の女性のライフサイクルの変容、第7章産業構造の変動と社会病、第8章薬害・医原病の多発とその背景、第9章「認定」と「補償」の責任論、第10章精神障害者と「こころを病む」人びと、第11章重症心身障害児(者)の歩み、第12章寝たきり・痴呆老人の戦後史、第13章難病患者の苦悩と挑戦の!!どれも興味深い。 第2部は川上武の書下ろしとなるが、表題である「現代医療のパラダイム転換と病人・障害者」を臨床医である著者が書いたところに意味がある。第1章脳死・臓器移植の軌跡、第2章性革命から生殖革命へ、第3章21世紀の死と生死観、第4章情報技術(IT)革命・ゲノム革命と病人・障害者、のそれぞれの論考は十分に説得力のあるものである。 また、単なる無味乾燥な歴史叙述ではなく、縦横無尽に小説やエッセイが引用されていることは、こうした本の取っ付きの悪さをある程度カバーしている、あとがきにあるように医療・福祉の関係者はぜひ読んで欲しい。もちろん一般読者にとっても知的興奮あふれる書物である事は保障できると思う。
 病人の目から見た現代医療批判 病人の目から見た現代医療批判
半世紀近くの評論活動を反映した川上武氏渾身の力作である。 二部構成で、第1部は川上武門下の研究者(それぞれの方が実践的な医療従事者であることは川上武氏の選択の視点が、たんなる研究者にはないことを示すものだろう)が各論史を書いたもの。第1章戦争と病人、第2章経済復興期の病人、第3章高度経済成長から成人病の時代へ、第4章リハビリテーション医療の登場、第5章妊娠・出産と乳児死亡・未熟児の動向、第6章戦後の女性のライフサイクルの変容、第7章産業構造の変動と社会病、第8章薬害・医原病の多発とその背景、第9章「認定」と「補償」の責任論、第10章精神障害者と「こころを病む」人びと、第11章重症心身障害児(者)の歩み、第12章寝たきり・痴呆老人の戦後史、第13章難病患者の苦悩と挑戦のどれも興味深い。 第2部は川上武の書下ろしとなるが、表題である「現代医療のパラダイム転換と病人・障害者」を臨床医である著者が書いたところに意味がある。第1章脳死・臓器移植の軌跡、第2章性革命から生殖革命へ、第3章21世紀の死と生死観、第4章情報技術(IT)革命・ゲノム革命と病人・障害者、のそれぞれの論考は十分に説得力のあるものである。 また、単なる無味乾燥な歴史叙述ではなく、縦横無尽に小説やエッセイが引用されていることは、こうした本の取っ付きの悪さをある程度カバーしている、あとがきにあるように医療・福祉の関係者はぜひ読んで欲しい。もちろん一般読者にとっても知的興奮あふれる書物である事は保障できると思う。
| 



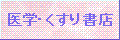












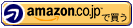
 4
4
 5
5

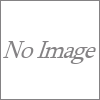

 4.5
4.5
 3.5
3.5 正直期待はずれではある
正直期待はずれではある


